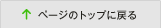2022.03.20
山本挙志の作品について

「そこに灰がある、ここでは
なくてそこに、まるで語られ
るべき物語のようにある」 ジャック・デリダ
ニューペインティングの影響のもと始まった山本挙志のキャリアは間もなく作家自身の異和感によって停滞することになった。
描きたいという視覚的な志向性と、「これではない」という手の指向性(≒嗜好性)による漠たる葛藤がその原因のひとつだった。自身のスタイルに異和を感じ続けていた作家は、その後10年以上アルバイトで生計を保ちながら、目と手の他者性の揺らぎに戸惑いつつ、創作活動を続けていた。その間には、「出来ない」という感覚と、美術家のエゴに対する嫌悪感も相俟って「絵画」を断念することも考えたという。